сђј90ТГ│сЂ«т╣ИудЈУФќсђЈсђїУфЇуЪЦуЌЄ№╝ЮС║║ућЪсЂ«ухѓсѓЈсѓісђЇсЂДсЂ»сЂфсЂё№╝Ђ
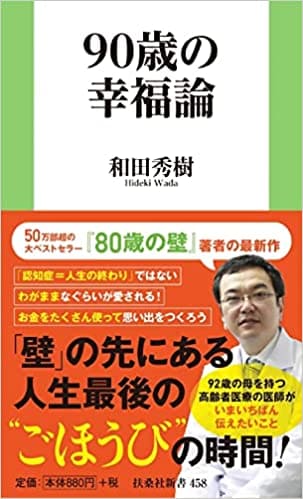
тњїућ░уДђТе╣сЂЋсѓЊУЉЌсђј90ТГ│сЂ«т╣ИудЈУФќсђЈ
50СИЄжЃеУХЁсЂ«тцДсЃЎсѓ╣сЃѕсѓ╗сЃЕсЃ╝сђј80ТГ│сЂ«тБЂсђЈсѓёсђј60ТГ│сЂІсѓЅсЂ»сѓёсѓісЂЪсЂёТћЙжАїсђЈсЂ«УЉЌУђЁсЃ╗тњїућ░уДђТе╣сЂЋсѓЊУЉЌсђј90ТГ│сЂ«т╣ИудЈУФќсђЈсЂїТЅХТАЉсѓѕсѓітѕіУАїсЂЋсѓїсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
92ТГ│сЂ«Т»ЇсѓњТїЂсЂцжФўжйбУђЁтї╗уЎѓсЂ«тї╗тИФсЂїсЂёсЂЙсЂёсЂАсЂ░сѓЊС╝ЮсЂѕсЂЪсЂёсЂЊсЂе
РЌєсђїУфЇуЪЦуЌЄ№╝ЮС║║ућЪсЂ«ухѓсѓЈсѓісђЇсЂДсЂ»сЂфсЂё
сђљТюгТЏИP111№йъсѓѕсѓіТіюу▓ІсђЉ
УфЇуЪЦуЌЄсЂ«уЌЄуіХсЂїжђ▓сѓЊсЂасЂесЂЌсЂдсѓѓсђЂсЂЎсЂ╣сЂдсЂ«УЃйтіЏсЂїтц▒сѓЈсѓїсѓІсѓЈсЂЉсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂсЂёсЂЈсЂцсЂІсЂ«УЃйтіЏсЂ»Т«ІсѓіуХџсЂЉсЂЙсЂЎсђѓсЂфсЂІсЂДсѓѓсђЂУЄфтѕєсЂ«У║ФсЂ«тЇ▒жЎ║ТђДсѓњТёЪсЂўсѓІУЃйтіЏсЂ»сѓѓсЂ»сѓётІЋуЅЕуџёТюгУЃйсЂфсЂ«сЂДсђЂТюђтЙїсЂ«ТюђтЙїсЂЙсЂДуЎ║ТЈ«сЂЋсѓїсѓІсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂёсЂІсЂеТђЮсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
УфЇуЪЦуЌЄсЂ«сЂ▓сЂесѓіТџ«сѓЅсЂЌсѓѓтЇ▒сЂфсЂёсЂеУђЃсЂѕсѓЅсѓїсЂїсЂАсЂДсЂЎсЂїсђЂт«ЪсЂ»УфЇуЪЦуЌЄТѓБУђЁсЂЋсѓЊсЂДсЂ▓сЂесѓіТџ«сѓЅсЂЌсѓњсЂЌсЂдсЂёсѓІТќ╣сЂ»тцДтІбсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂІсЂфсѓіжЄЇсЂёС║║сЂДсѓѓсЂ▓сЂесѓіТџ«сѓЅсЂЌсѓњсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
УфЇуЪЦуЌЄсЂФсЂфсЂБсЂЪсЂІсѓЅсЂесЂёсЂБсЂдсѓѓсђЂсЂёсЂЇсЂфсѓіСйЋсѓѓсЂІсѓѓсЂїсЂДсЂЇсЂфсЂЈсЂфсѓІсѓЈсЂЉсЂДсЂ»сЂѓсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
сђїТ«ІтГўТЕЪУЃйсђЇсЂесЂёсЂБсЂдсђЂТўћсЂІсѓЅу┐њТЁБсЂЦсЂЉсЂдсЂёсЂЪУАїтІЋсЂфсѓЅсЂ░сђЂУфЇуЪЦуЌЄсЂФсЂфсЂБсЂдсѓѓтцЅсѓЈсѓЅсЂџсЂФсЂДсЂЇсѓІсЂЊсЂесѓѓсЂЪсЂЈсЂЋсѓЊсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сђїУфЇуЪЦуЌЄ№╝ЮС║║ућЪсЂ«ухѓсѓЈсѓісђЇсЂасЂеТѓ▓Уд│сЂЌсЂфсЂёсЂДсЂ╗сЂЌсЂёсЂеТђЮсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
РЌєсђїтБЂсђЇсЂ«тЁѕсЂФсЂѓсѓІС║║ућЪТюђтЙїсЂ«РђюсЂћсЂ╗сЂєсЂ│РђЮсЂ«ТЎѓжќЊ№╝Ђ
сђїС║║ућЪ100т╣┤ТЎѓС╗БсђЇсЂеУеђсѓЈсѓїсЂдС╣ЁсЂЌсЂёсЂДсЂЎсЂїсђЂ92ТГ│сЂ«Т»ЇсѓњТїЂсЂцжФўжйбУђЁтї╗уЎѓсЂ«тї╗тИФсЃ╗тњїућ░уДђТе╣сЂЋсѓЊсЂїуЏ«сЂ«тйЊсЂЪсѓісЂФсЂЌсЂдсЂЇсЂЪсЂіт╣┤т»ёсѓісЂЪсЂАсЂІсѓЅтЙЌсЂЪсђЂсђїт╣ИсЂЏсЂф90С╗БсЂФсЂфсѓІсЂЪсѓЂсЂФт┐ЁУдЂсЂфсЂЊсЂесђЇсѓњсђЂсђїтЂЦт║исђЇсђїсЂіжЄЉсђЇсђїућЪТ┤╗у┐њТЁБсђЇсђїС╗ІУГисђЇсЂфсЂЕсЂЋсЂЙсЂќсЂЙсЂфУд│уѓ╣сЂІсѓЅу┤╣С╗ІсЂЌсЂдсЂёсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
60ТГ│С╗ЦСИісЂ«жФўжйбУђЁсѓё90С╗БсЂ«УдфсѓњТїЂсЂцС║║сЂ»т┐ЁУфГсЂ«СИђтєісЂДсЂЎсђѓ
ТюгТЏИсЂ«ТДІТѕљ
№╝ЉуФасђђт╣ИсЂЏсЂфсЂіт╣┤т»ёсѓісЂ«ТЮАС╗Х
сЃ╗т╣┤т»ёсѓісЂїСИЇт╣ИсЂасЂфсѓЊсЂдсђЂУф░сЂїУеђсЂБсЂЪ
сЃ╗УђЂсЂёсЂ»С║║сЂеТ»ћсЂ╣сѓЅсѓїсЂфсЂё
сЃ╗УдЂС╗ІУГисѓњжЂ┐сЂЉсЂЪсЂЉсѓїсЂ░
сђђсђїсЃЋсЃгсѓцсЃФсѓхсѓцсѓ»сЃФсђЇсЂФжЎЦсѓІсЂф
сЃ╗ТёЏсЂЋсѓїсѓІсЂіт╣┤т»ёсѓісЂеТёЏсЂЋсѓїсЂфсЂёсЂіт╣┤т»ёсѓісЂ«тБЂ
№╝њуФасђђС╗ќС║║сѓёжЂЊтЁисѓњжа╝сЂБсЂдугг№╝њсЂ«С║║ућЪсѓњТЦйсЂЌсѓђ№╝Ђ
сЃ╗УБюУЂ┤тЎесЂДУфЇуЪЦуЌЄсЂ«тЁЦсѓітЈБсѓњжЂасЂќсЂЉсѓІ
сЃ╗№╝њтЏъжфеТіўсЂЌсЂдсѓѓТГЕсЂЉсѓІ№╝Ў№╝њТГ│сЂ«Т»Ї
сЃ╗жФўжйбУђЁсЂЊсЂЮТЃЁта▒уЎ║С┐АсѓњсЂЌсЂдсЂ╗сЂЌсЂё№╝Ђ
сЃ╗сђїСИђУХ│тЁѕсЂФсЂіСИќУЕ▒сЂФсЂфсѓІсЂГсђЇсЂ«у▓ЙуЦъ
сЃ╗сЂфсЂют«ХТЌЈсЂФС╗ІУГисѓњсЂЋсЂЏсЂфсЂёсЂ╗сЂєсЂїсЂёсЂёсЂ«сЂІ№╝Ъ
№╝ЊуФасђђтї╗УђЁсѓњС┐АсЂўсЂЎсЂјсЂџтЂЦт║исЂфжФўжйбУђЁсЂФ
сЃ╗сђїтђІС║║ти«сђЇсЂїуёАУдќсЂЋсѓїсѓІуЈЙС╗Бтї╗тГд
сЃ╗сђїУфЇуЪЦуЌЄ№╝ЮС║║ућЪсЂ«ухѓсѓЈсѓісђЇсЂДсЂ»сЂфсЂё
сЃ╗сђїсЂЇсѓЊсЂЋсѓЊсЂјсѓЊсЂЋсѓЊсђЇсЂ«сѓѕсЂєсЂФт╣ИсЂЏсЂфсЂіт╣┤т»ёсѓісЂФ
сЃ╗УдІжђЃсЂЋсѓїсЂїсЂАсЂфсђїжФўжйбУђЁсЂ«сЂєсЂцуЌЁсђЇ
№╝ћуФасђђУђЂтЙїсЂ«сЂіжЄЉсѓњт┐ЃжЁЇсЂЌсЂЎсЂјсЂдсЂёсЂЙсЂЏсѓЊсЂІ№╝Ъ
сЃ╗тЁЃТ░ЌсЂфсЂєсЂАсЂФсЂіжЄЉсѓњСй┐сЂёсЂЙсЂЈсѓЇсЂє№╝Ђ
сЃ╗сђїухѓТ┤╗сђЇсѓњсЂісЂЎсЂЎсѓЂсЂЌсЂфсЂёуљєућ▒сЂесЂ»№╝Ъ
сЃ╗тГљСЙЏсЂФУ▓АућБсѓњТ«ІсЂЌсЂдсѓѓсѓ▒сЃ│сѓФсЂФсЂфсѓІсЂасЂЉ
сЃ╗С╗ІУГисЂФт┐ЁУдЂсЂфжЄЉжАЇсЂесЂ»№╝Ъ
сЃ╗ућЪТ┤╗С┐ЮУГисЂ»ТЂЦсЂџсЂІсЂЌсЂЈсЂфсЂё№╝Ђ
сЃ╗уљєТЃ│уџёсЂасЂБсЂЪуЦќТ»ЇсЂ«УЉгт╝Ј
сЃ╗тЈ»УЃйсЂфжЎљсѓісђЂтЃЇсЂЈсЂесЂёсЂєжЂИТіъУѓбсѓѓ
№╝ЋуФа РђюсЂћсЂ╗сЂєсЂ│РђЮсЂ«ТЎѓжќЊсѓњТюђтцДжЎљТ║ђтќФсЂЎсѓІућЪТ┤╗у┐њТЁБ
сЃ╗жФўжйбУђЁсЂЊсЂЮТаёжціСЙАсЂїжФўсЂёсѓѓсЂ«сѓњжБЪсЂ╣сѓІсЂ╣сЂЇ
сЃ╗сѓ│сЃгсѓ╣сЃєсЃГсЃ╝сЃФтђцсѓњСИісЂњсѓІсЂ╣сЂЇтї╗тГдуџёсЂфуљєућ▒
сЃ╗сђїУЄфуѓісЂЌсЂфсЂЉсѓїсЂ░сЂёсЂЉсЂфсЂёсђЇсЂФуИЏсѓЅсѓїсѓІсЂф
сЃ╗сђїУё│сЃѕсЃгсђЇсѓѕсѓісѓѓсѓбсѓдсЃѕсЃЌсЃЃсЃѕ№╝Ђ
сЃ╗УІЦсЂёуЋ░ТђДсЂесЂ«ТјЦуѓ╣сѓњсЂцсЂЈсѓЇсЂє
сЃ╗сђїУІЦсЂЦсЂЈсѓісђЇсЂ»сЂДсЂЇсѓІсЂасЂЉсЂЌсЂЪсЂ╗сЂєсЂїсЂёсЂё
сЃ╗сђїжЃйтљѕсЂ«сѓѕсЂёсЂіт╣┤т»ёсѓісђЇсЂФсЂфсѓЅсЂфсЂё№╝Ђ
РђдРђдсЂфсЂЕ
УЉЌУђЁсЃЌсЃГсЃЋсѓБсЃ╝сЃФ
УЉЌУђЁсЂ«тњїућ░уДђТе╣№╝ѕсѓЈсЂасЃ╗сЂ▓сЂДсЂЇ№╝ЅсЂЋсѓЊсЂ»сђЂ1960т╣┤ућЪсЂЙсѓїсђЂтцДжўфт║ютЄ║У║ФсђѓТЮ▒С║гтцДтГдтї╗тГджЃетЇњТЦГсђѓу▓ЙуЦъуДЉтї╗сђѓтЏйжџЏтї╗уЎѓудЈуЦЅтцДтГдТЋЎТјѕсђѓсЃњсЃЄсѓГсЃ╗сЃ»сЃђсЃ╗сѓцсЃ│сѓ╣сЃєсѓБсЃєсЃЦсЃ╝сЃѕС╗БУАесђѓСИђТЕІтцДтГдтЏйжџЏтЁгтЁ▒Тћ┐уГќтцДтГджЎбуЅ╣С╗╗ТЋЎТјѕсђѓтиЮт┤јт╣ИуЌЁжЎбу▓ЙуЦъуДЉжАДтЋЈсђѓ
ТЮ▒С║гтцДтГдтї╗тГджЃежЎёт▒ъуЌЁжЎбу▓ЙуЦъуЦъухїуДЉтіЕТЅІсђЂу▒│тЏйсѓФсЃ╝сЃФсЃ╗сЃАсЃІсЃ│сѓгсЃ╝у▓ЙуЦътї╗тГдТаАтЏйжџЏсЃЋсѓДсЃГсЃ╝сѓњухїсЂдсђЂуЈЙтюесђЂтњїућ░уДђТе╣сЂЊсЂЊсѓЇсЂеСйЊсЂ«сѓ»сЃфсЃІсЃЃсѓ»жЎбжЋисђѓжФўжйбУђЁт░ѓжќђсЂ«у▓ЙуЦъуДЉтї╗сЂесЂЌсЂдсђЂ30т╣┤С╗ЦСИісЂФсѓЈсЂЪсЂБсЂджФўжйбУђЁтї╗уЎѓсЂ«уЈЙта┤сЂФТљ║сѓЈсЂБсЂдсЂёсѓІсђѓ
сђј70ТГ│сЂїУђЂтїќсЂ«тѕєсЂІсѓїжЂЊсђЈ(УЕЕТЃ│уцЙТќ░ТЏИ)сђЂсђјтЁГтЇЂС╗БсЂеСИЃтЇЂС╗Б т┐ЃсЂеСйЊсЂ«ТЋ┤сЂѕТќ╣сђЈ(сЃљсѓИсЃфсѓ│)сђЂсђјУђЂтЙїсЂ»УдЂжаўсђЈ(т╣╗тєгУѕј)сђЂсђјсЃљсѓФсЂесЂ»СйЋсЂІсђЈсђјТёЪТЃЁсЃљсѓФсђЈсђј80ТГ│сЂ«тБЂсђЈ(сЂесѓѓсЂФт╣╗тєгУѕјТќ░ТЏИ)сЂфсЂЕУЉЌТЏИтцџТЋ░сђѓ
 | №╝Ў№╝љТГ│сЂ«т╣ИудЈУФќ (ТЅХТАЉуцЙТќ░ТЏИ) тњїућ░ уДђТе╣ (УЉЌ) |
РЌєсђјсЃљсЃісЃісЂ«сЂЎсЂћсЂётЂЦт║ижЋит»┐тіЏсђЈжФўУАђтюДсђЂжФўУАђу│ќсђЂУѓЦТ║ђсђЂУЃЃУЁИсЂ«СИЇУф┐сЂІсѓЅсђЂтЁЇуќФтіЏсђЂСЙ┐уДўсђЂСИЇуюасђЂУѓїсЂ«УІЦУ┐ћсѓісЂЙсЂД№╝Ђ | ТюгсЂ«сЃџсЃ╝сѓИ
РЌєсђј75ТГ│сЂІсѓЅсѓёсѓЂсЂдт╣ИсЂЏсЂФсЂфсѓІсЂЊсЂесђЈСИђТ░ЌсЂФУђЂсЂЉсѓІС║║сђЂТЌЦсЂћсЂесЂФУІЦсђЁсЂЌсЂЈсЂфсѓІС║║сЂ«ти«сЂесЂ»№╝Ъ | ТюгсЂ«сЃџсЃ╝сѓИ
РЌєсђј70ТГ│сЂІсѓЅсЂ»сЂЊсѓїсѓњжБЪсЂ╣сѓІ№╝ЂсђЈSTOP№╝ЂСйјТаёжцісђђжБЪТЮљсЂ«жЂИсЂ│Тќ╣сЂїтЂЦт║исѓњтидтЈ│сЂЎсѓІ№╝Ђ | ТюгсЂ«сЃџсЃ╝сѓИ
РЌєсђјсђїУё│сЂ«ТаёжціСИЇУХ│сђЇсЂїУђЂтїќсѓњТЌЕсѓЂсѓІ№╝ЂсђЈ60ТГ│сЂІсѓЅсЂ«сђїУђЂсЂЉсЂфсЂёСйЊсђЇсЂФтцЅсѓЈсѓІжБЪу┐њТЁБсЂесЂ»№╝Ъ | ТюгсЂ«сЃџсЃ╝сѓИ









