梅田 蔦屋書店「文学コンシェルジュ」北田博充さん『本屋のミライとカタチ -新たな読者を創るために-』が刊行
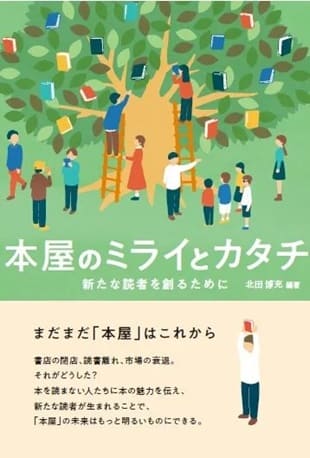
梅田 蔦屋書店の店長であり、文学コンシェルジュでもある北田博充さんの8年ぶりの著書『本屋のミライとカタチ -新たな読者を創るために-』がPHP研究所より2月16日(金)に刊行されます。
これからの本屋を面白くするアイデアが満載!
『本屋のミライとカタチ -新たな読者を創るために-』は、本の魅力を多角的に伝えている人の活動、他業種の復活事例などから、書店の将来の可能性を探る本です。
「書店員」だけではなく、「本の魅力を伝える人」すべてを広義の「本屋」ととらえ、未来の読者を創るために活動されている、元高校国語科教諭・嘉登隆さんや、小説紹介クリエイターのけんごさんなどをインタビューで紹介しています。
若者の読書離れ、書店数の減少等、昨今メディアが取り上げる「本にまつわるニュース」はネガティブなものが増えていますが、その一方で全国各地にユニークな独立系書店が開業したり、一年に何度かは雑誌で「本屋特集」が組まれたりするなど、本を愛し本屋を愛する人たちの熱気は冷めることがありません。
本書刊行の目的は、「新たな読者層の創出」により出版業界を活性化していくことです。そのためには、「普段本を読まない人」や「書店に足を運ぶ習慣がない人」たちに焦点を当て、このような方々をどのように顧客化すればよいかを考える必要があります。
その具体的な手法として、出版業界内の有識者のみならず、出版業界外で本に深く関わる人たちにインタビューをすることで、これまでの「本屋本」で言及できていなかった打開策を明示し、読者自身が自分の行動範囲の中で「本の魅力を伝える」ようになることを目指します。
本書の構成
第一章 本屋とは誰か?
インタビュー: 芹澤連(コレクシア)
第二章 本への入口を創る
第一節 高校国語科教諭は本屋か?
インタビュー: 嘉登隆(元高校国語科教諭)
コラム: 田口幹人(未来読書研究所)「これからの読者のために」
第二節 TikTokerは本屋か?
インタビュー: けんご(小説紹介クリエイター)
コラム: 粕川ゆき(いか文庫)「本屋というモノとコト」
第三章 異業種から学ぶ
第一節 異業種から学ぶ「新規顧客創出法」
インタビュー: 瀬迫貴士(ページ薬局)
コラム: 内沼晋太郎(numabooks)「〈本×〇〇〉こそが王道です」
第二節 プロレス業界のV字回復と本屋の未来
インタビュー: 高木三四郎(CyberFight)
コラム: 伊野尾宏之(伊野尾書店)「伊野尾書店がDDTから学んだこと」
第四章 新たな読者を創るために
座談会:有地和毅(日本出版販売)、花田菜々子(蟹ブックス)、森本萌乃(MISSION ROMANTIC)、山下優(青山ブックセンター)
著者プロフィール

北田博充さん(梅田 蔦屋書店)
北田博充(きただ・ひろみつ)さんは、大学卒業後、出版取次会社に入社し、2013年に本・雑貨・カフェの複合店「マルノウチリーディングスタイル」を立ち上げ、その後リーディングスタイル各店で店長を務める。2016年にひとり出版社「書肆汽水域」(https://kisuiiki.com/)を立ち上げ、長く読み継がれるべき文学作品を刊行している。2016年、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に入社。現在、梅田 蔦屋書店で店長を務める傍ら、出版社としての活動を続けている。2020年には本・音楽・食が一体となった本屋フェス「二子玉川 本屋博」を企画・開催し、2日間で3万3,000人が来場。
著書に『これからの本屋』(書肆汽水域)、共編著書に『まだまだ知らない 夢の本屋ガイド』(朝日出版社)、共著書に『本屋の仕事をつくる』(世界思想社)がある。

| 本屋のミライとカタチ 新たな読者を創るために(仮) 北田 博充 (著, 編集) 新たな形の本屋を創出する人の気概、本の魅力を多角的に伝えている人の活動、他業種の復活事例などから、書店の将来の可能性を探る。 |
◆『カレーの時間』刊行記念!著者・寺地はるなさん×『宙ごはん』町田そのこさんトークイベントを開催 | 本のページ
◆「SFカーニバル 2022」に先駆け、選書フェア「日本SF作家クラブが選ぶ偏愛SF200とちょっと」が代官山&梅田 蔦屋書店で開催 | 本のページ
◆「SFカーニバル 2022」が代官山 蔦屋書店&梅田 蔦屋書店で開催 よしながふみさん『大奥』への日本SF大賞贈賞式も | 本のページ
◆「梅田 蔦屋書店」人文コンシェルジュ・三砂慶明さん読書エッセイ『千年の読書』が刊行 | 本のページ









