9月18日は「敬老の日」――翔泳社が在宅介護関連6タイトルを期間限定で全文無料公開

翔泳社は敬老の日にあわせて、同社より刊行された在宅介護関連書籍6タイトルを2023年9月25日(月)まで全ページを無料公開中です。
家族の介護をする人たちに向けた本を全ページ無料公開
9月18日は「敬老の日」です。翔泳社では、敬老の日にあわせて、大切な家族を介護する人たちに向けた、「介護」への理解を深められる在宅介護の関連書を期間限定で全文無料公開します。
専門家がわかりやすく解説したノウハウは、いま介護をしている人にも、介護に備えて情報収集している人にも役立ちます。
対象となるのは、在宅介護での困りごとに役立つ現実的なノウハウをまとめた実用書『はじめての在宅介護』シリーズ4冊と、離れて暮らす親の認知症介護の本、認知症の予防法に関する本の計6タイトルです。
さらに、これら無料公開の6タイトルと『親が倒れた!親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第3版』『親の見守り・介護をラクにする道具・アイデア・考えること』の全8タイトルについて、Amazonで10%ポイント還元、翔泳社の通販サイトSEshopで10%割引されるキャンペーンを同期間内に開催します。
■公開期間:2023年9月11日(月)~9月25日(月)
■無料公開対象書籍:
◎「家族介護」のきほん 経験者の声に学ぶ、介護の「困り事」「不安」への対処法
◎「食べる」介護のきほん 誤嚥を防いで食の楽しみをキープする、食事介助&お口のケア
◎「家トレ」のきほん 飽きずに楽しく続けられる! 「自分で動ける」を維持するトレーニング
◎「認知症の人」への接し方のきほん あなたの家族に最適な方法が見つかる!「場面別」かかわり方のポイント
◎親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと
◎科学的に正しい認知症予防講義
★特設ぺージ:https://www.shoeisha.co.jp/book/kaigo
無料公開対象書籍の概要
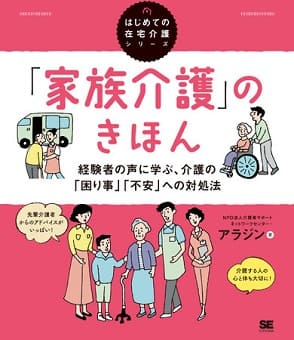
■『「家族介護」のきほん 経験者の声に学ぶ、介護の「困り事」「不安」への対処法』
著者:NPO法人 介護者サポートネットワークセンター・アラジン
20年以上にわたり、さまざまな介護している家族の相談やサポートを続けているNPO法人の「アラジン」。「アラジン」の蓄積された経験や豊富な相談事例をもとに、理想じゃない、介護者の暮らしや人生に寄り添った、リアルな介護の乗り切り方を伝授します。「気持ちが晴れないとき」「疲れたとき」「孤独を感じているとき」「要介護者に腹が立ってしょうがないとき」など、先輩介護者からのアンケートコメントは必読!「わかるわかる」と共感できて、あなたの介護がラクになります。
【著者 NPO法人 介護者サポートネットワークセンター・アラジンからのコメント】
突然はじまる介護。不安や戸惑いからストレスを抱えることが多いものです。これまで介護者支援の現場で、ケアラーの方々からさまざまな悩みや不安、また介護の工夫についてなど、多くの声を聴いてきました。そうした経験談を元に、介護が迫っている方、介護の初期の方に、知識や情報、介護の向き合い方などをあらかじめ知っていただき、何らかの道しるべになればと思い、まとめた一冊です。あなたは決して一人ではありません。多くの仲間たちがいます。
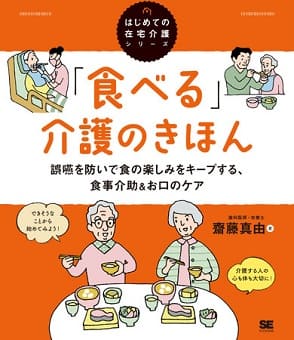
■『「食べる」介護のきほん 誤嚥を防いで食の楽しみをキープする、食事介助&お口のケア』
著:齋藤真由さん
「口から食べること」は心身の健康や生活の質にも直結するので、できるだけ美味しく・楽しく食べてほしい。とはいえ、食事の用意や介助、お口のケアを手厚く行うのは負担が大きい。本書では、栄養士資格も持つ歯科医師の著者が、長年の摂食嚥下診療や口腔ケア指導、家庭や施設への訪問診療の経験をもとに、食事場面での困り事への対応、誤嚥予防のポイント、家庭でできる口腔ケア、入れ歯についての疑問や、訪問歯科の利用など、「介護される人」だけでなく「介護する人」の実情もふまえたノウハウや考え方を提案します。
【著者 齋藤真由さんからのコメント】
「お家のごはんが食べられる」というのは、在宅介護だからこそ得られる喜びです。しかし、1日3回やってくる食事が本人やご家族にとって負担になっていたり、「本当にこれでいいの?」という不安を抱えているご家族が多くいらっしゃるのも事実。そこで本書では、食事やお口のケアについて、キモをおさえて上手に手抜き(=仕事の効率化)できるようなヒントを詰め込みました。介護に正解はありませんが、本書のヒントを生かし、介護する人・される人の負担や不安が少しでも減ることを心から願っています。
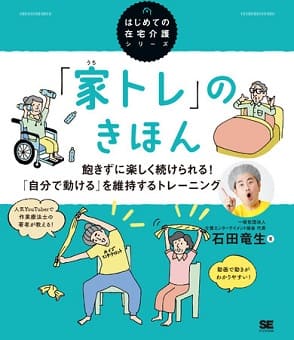
■『「家トレ」のきほん 飽きずに楽しく続けられる! 「自分で動ける」を維持するトレーニング』
著:石田竜生さん
高齢者が運動を習慣化して「自分で動ける」状態を維持することは、介護予防・介護度の進行予防につながります。本書には「楽しく飽きずに続けられる」をテーマに、お家で気軽に取り組めるトレーニング=家(うち)トレを50種類以上収録。高齢者や介護施設の関係者にも大好評のYouTubeチャンネル『介護エンターテイメント脳トレ介護予防研究所』で3万人超の登録者数を持つ著者が、やる気を保って続けられる体操を写真と動画でわかりやすく解説します。
【著者 石田竜生さんからのコメント】
「運動の継続」は、介護予防や心身の状態を維持していくためにとても大切なことです。コロナの影響で外出が思うようにできなくなったいま、お家で継続しやすい体操を紹介したのがこの『「家トレ」のきほん』です。本書をはじめとした「はじめての在宅介護シリーズ」がみなさんの心の支えになり、前向きな気持ちでワクワクする毎日が続くように願っています。また、はじめて介護に直面すると不安でいっぱいになるかと思います。そんなときはぜひ介護のプロにも頼ってみてください。
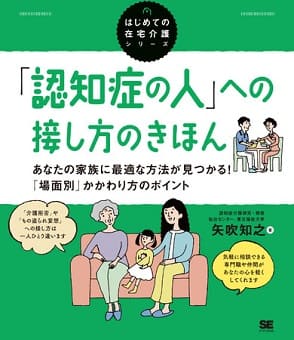
■『「認知症の人」への接し方のきほん あなたの家族に最適な方法が見つかる!「場面別」かかわり方のポイント』
著:矢吹知之さん
本書では、「困った行動」を場面ごとに紹介し、その背景にあるさまざまな原因をひも解きながら、一人ひとりの感情を理解して、その人に本当に合った接し方を見つけるための方法を具体的に解説しています。はじめて認知症介護をする方はもちろんのこと、「本やインターネットに書いてある通りにやってみたけれど上手くいかなかった」という人にも、ぜひ読んでいただきたい一冊です。
【著者 矢吹知之さんからのコメント】
いま認知症は、インターネットやテレビの情報があふれ、その情報の海におぼれそうになる感覚になることがありますよね。そんな時、この本を手に取ってみてください。認知症の本人・家族のたくさんの声から、多くの人が戸惑う事柄や長い介護生活の支えになった考え方をまとめました。認知症の人との関係性は一日で改善するものではありませんが、この本をヒントにしていただくことで、少しずつでも確実に、良い方向に変わっていくはずです。
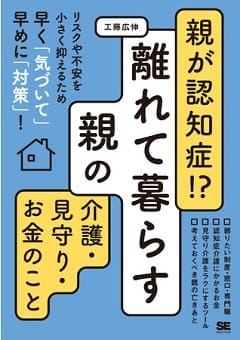
■『親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと』
著:工藤広伸さん
遠距離介護の実践者でもある経験豊富な著者が、実際に「親と離れた認知症介護」の中で培ったノウハウを伝授します。リスクや不安を小さく抑えるためには、早く「気づいて」早めに「対策」することが大切です。頼りたい制度・窓口・専門職や、認知症介護にかかるお金、見守り介護をラクにするツールなど、いますぐ役立つ具体的な情報が満載です。
【著者 工藤広伸さんからのコメント】
2023年6月に、認知症基本法が参議院で可決成立しました。認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるよう国として施策を推進していくようです。認知症になったからといって、何もできなくなるわけではありません。親と離れて暮らしていても、認知症であっても住み慣れた家で生活は可能で、私は10年以上実践しています。その具体的なノウハウをまとめたこの本を活用して頂けるとうれしいです。

■『科学的に正しい認知症予防講義』
著:浦上克哉さん
日本認知症予防学会理事長も務める認知症予防の第一人者が、現時点で、科学的に最も理にかなった認知症予防法と、その実践方法を講義形式でわかりやすく紹介します。認知症を予防したいなら知っておくべき「12の発症リスク因子」や、科学的に効果が実証された「運動」と「脳の鍛え方」(知的活動)の方法について解説します。科学的根拠がしっかりした認知症予防法に取り組みたい人におすすめの一冊です。
【著者 浦上克哉さんからのコメント】
認知症患者数が急激に増加し2025年には700万人(65才以上の5人に1人)が認知症という時代を迎えようとしています。誰もがなりうる病気であり、多くの高齢者が認知症予防をしたいと思っておられます。そのニーズに応えるために認知症のさまざまな予防法の情報や商品が氾濫している状況にあります。そこで本書は現時点で科学的に信頼性が高い予防法を厳選して紹介し、本当に効果のある認知症予防を一人でも多くの人に実践して欲しいという思いで執筆しました。是非、ご一読頂ければ幸いに存じます。
 | 「家族介護」のきほん 経験者の声に学ぶ、介護の「困り事」「不安」への対処法(はじめての在宅介護シリーズ) NPO法人 介護者サポートネットワークセンター・アラジン (著) 「介護する人」に寄り添う、在宅介護の実用書シリーズ新登場! 20年以上にわたり、さまざまな介護している家族の相談やサポートを続けているNPO法人の「アラジン」。 介護ブログ「ヘルパーおかん。アラフィフ専業主婦からのハローワーク。」で有名な漫画家、ゆらりゆうらさんの書下ろし4コマ漫画を多数収載。現役介護福祉士として働きつつ、実際に家族を介護中の実体験を元にした、笑いと涙の漫画です。 |
 | 「食べる」介護のきほん 誤嚥を防いで食の楽しみをキープする、食事介助&お口のケア(はじめての在宅介護シリーズ) 齋藤 真由 (著) 「介護する人」に寄り添う在宅介護の実用書シリーズ新登場! ・いつもの食事が食べにくそう 「口から食べること」は心身の健康や生活の質にも直結するので、できるだけ美味しく・楽しく食べてほしい。 本書では、栄養士資格も持つ歯科医師の著者が、長年の摂食嚥下診療や口腔ケア指導、家庭や施設への訪問診療の経験をもとに、「食べる力」をキープするために知っておきたいことを、イラストとともにわかりやすく解説します。 食事場面での困り事への対応、誤嚥予防のポイント、家庭でできる口腔ケア、入れ歯についての疑問や、訪問歯科の利用など、「介護される人」だけでなく「介護する人」の実情もふまえたノウハウや考え方を提案します。 |
 | 「家トレ」のきほん 飽きずに楽しく続けられる! 「自分で動ける」を維持するトレーニング(はじめての在宅介護シリーズ) 石田竜生 (著) 高齢者の運動は、「楽しく」「飽きない」が継続のカギ! 高齢者や介護施設の関係者にも大好評のYouTubeチャンネル『介護エンターテイメント脳トレ介護予防研究所』で3.3万人超の登録者数を持つ著者が、やる気を保って続けられる体操を写真と動画でわかりやすく解説します。 【こんなお悩みがある方におすすめ】 【本書を読むと……】 【本書で紹介する体操】 ■プラスワン家トレ ■脳を鍛える家トレ |
 | 「認知症の人」への接し方のきほん あなたの家族に最適な方法が見つかる!「場面別」かかわり方のポイント(はじめての在宅介護シリーズ) 矢吹 知之 (著) 「ネットや本で学んだ通りに対応しているのに上手くいかない…」 【この本を読んで身につくこと】 「何度も同じことを聞かれて疲れてしまった」 このような「困った行動」は、記憶障害などの認知症による影響に加えて、本人が感じている不安、不信感などの感情が原因になって引き起こされます。 例えば、なかなかご飯を食べてくれないとき、記憶障害の影響でほんのちょっと前に食事をしたと思い込んでいれば、「早く食べてよ」と伝えても、納得しないばかりか不信感が増すばかりです。 また、感覚障害の影響でご飯の色や形が正しく認識できなければ、美味しそうに見えず、食べないということもあります。 箸の使い方がわからなくなってしまった場合は、それを身近な家族に指摘されて自尊心が傷つくことが怖くて、食事を嫌がっているのかもしれません。 このように、一見して同じ「食事拒否」という現象でも、その原因も、そのとき感じている気持ちも一人ひとり異なっています。 そのため、認知症の人への接し方には、「食事拒否には〇〇という対応すればよい」といった、万人に通じる答えは存在しないのです。 この本では、「困った行動」を場面ごとに紹介し、その背景にある様々な原因をひも解きながら、一人ひとりの感情を理解して、その人に本当に合った接し方を見つけるための方法を具体的に解説しています。 また、「認知症介護における家族支援」を専門とし、様々な家族を見てきた著者だから伝えることができる「認知症介護の心得」や「頼りになる相談先の見つけ方」などの実践的なノウハウも盛り込みました。 はじめて認知症介護をする方はもちろんのこと、「本やインターネットに書いてある通りにやってみたけれど上手くいかなかった」という人にも、ぜひ読んでいただきたい一冊です。 |
 | 親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと 工藤 広伸 (著) リスクや不安を小さく抑えるため早く「気づいて」早めに「対策」! 「母親の様子が、なんか最近おかしい気がする…」 離れて暮らす親が、心配になることがあります。 答えは当然NOです! 本書は、経験豊富な著者が、実際に「親と離れた認知症介護」の中で培った次のようなノウハウを皆様に伝授する本です! 著者は、認知症の祖母を遠距離介護後、悪性リンパ腫の父親を在宅介護で看取り、いまも認知症の母のため、東京と岩手を年間約20往復中。遠距離介護の実践者としては、なかなかの猛者です。 すべて著者が実践したものだからこそ、重みがあります。 ★★こんなあなたは要チェック! ★★ |
 | 科学的に正しい認知症予防講義 浦上 克哉 (著) 最高峰の医学論文で判明! 【科学的根拠がしっかりした認知症予防法に取り組みたい人におすすめ!】2025年には「高齢者の5人に1人(約750万人)が認知症」という時代がやってくるとされており、テレビや雑誌などでも様々な認知症予防法が紹介されています。 本書では、認知症予防の第一人者(日本認知症予防学会 理事長)が、現時点で、科学的に最も理にかなった認知症予防法と、その実践方法を講義形式でわかりやすく紹介していきます。 ◎自粛下でもできる!ウィズコロナ時代の認知症予防のコツも紹介 |
【関連】
▼はじめての在宅介護|翔泳社の本
◆江戸時代にも高齢者介護はあった! 﨑井将之さん『武士の介護休暇』が刊行 | 本のページ
◆“元祖ヤングケアラー”町亞聖さん『受援力』が刊行 | 本のページ
◆こころの雨は突然降りだす!東畑開人さん『雨の日の心理学』が刊行 | 本のページ
◆双葉社文芸総合サイト「COLORFUL podcast」スタート 降田天さん、斜線堂有紀さんへ著者インタビュー、湊かなえさんのオーディオブック「試し聴き」など | 本のページ








